【重要】この記事を読む上での注意点
本記事は、大学の試験制度に関する一般的な知識を提供するものです。しかし、大学のルールは、国公私立、学部、学年によって大きく異なります。「再試験」制度の有無、追試験の成績評価、GPAの計算方法など、重要な規定はあなたの大学独自のものである可能性が高いです。
この記事を鵜呑みにせず、必ずご自身の大学の「履修要覧(学生便覧)」で公式な規定を確認してください。
「期末試験、全然できなかった…終わったかもしれない…」
「体調不良で、大事な試験を受けられなかった…」
「これって、もしかして留年しちゃうの?」
試験期間が終わるこの時期、あなたの心は期待よりも不安でいっぱいかもしれませんね。
こんにちは!現役大学職員のシュウです。
毎年この時期になると、試験の結果を前に顔面蒼白になり、「どうしたらいいですか…」と私のところに駆け込んでくる学生が後を絶ちません。彼らの多くに共通しているのは、たった一つのこと。
それは、大学における「試験後のルール」を全く知らない、ということです。
大学職員として、そんな学生を何人も見てきました。「再試験」と「追試験」という、似ているようで全く意味が違う言葉。その違いを知らなかったばかりに、本来受けられるはずだった救済措置を逃し、進級や卒業が危うくなってしまうのです。
しかし、もう大丈夫です。この記事は、そんな悲劇を避けるための「お守り」です。
この記事を読み終える頃には、あなたは試験に関する様々な用語の違いを完全に理解し、万が一の事態に陥っても、冷静に、そして正しく行動できるようになっているはずです。
【結論】あなたは大丈夫?「試験後の行動」で運命が分かれる
結果を気にする前に、まず下の図を見てください。あなたが今、どの状況にいるのか。そして、次にどんな選択肢があるのか。大学における試験後のルートは、実はとてもシンプルです。
-
A.合格 (おめでとう!)単位修得!
-
B.不合格 (点数不足)➡️ ルート1:再試験(制度があり、条件を満たせば)
- ✅合格 → 単位修得(ただし成績は最低評価)
- ❌不合格 → 不可 (単位不認定)
➡️ ルート2:再試験制度なし or 条件外- ❌不可 (単位不認定)
-
C.欠席 (やむを得ない理由あり)➡️ ルート3:追試験
- ✅合格 → 単位修得(ただし成績評価は大学による)
- ❌不合格 → 不可 (単位不認定) or 再試験(大学による)
-
D.欠席 (無断)
- ❌不可 (単位不認定)
どうでしょうか。あなたが次に進むべき道が見えてきましたか?
ここからは、あなたの運命を左右する「再試験」と「追試験」という2つの重要なルートについて、大学職員の視点から詳しく解説します。
「再試験」とは? – 不合格だった場合の”敗者復活戦”
再試験とは、一言でいうと、「期末試験を受けたものの、合格点に届かなかった(不合格だった)学生」に対して、もう一度チャンスを与えるための救済措置です。まさに”敗者復活戦”ですね。
しかし、この敗者復活戦には、知っておくべき重要なルールがあります。
ルール①:「再試験制度」は普遍的ではない!【最重要】
これが最も重要です。まず、あなたの大学に「再試験」という制度自体が存在するか、存在するとしてあなたが対象になるかを確認する必要があります。
- 制度そのものが無い大学: 一橋大学のように「再試験は、行わない」と明確に定めている大学もあります。
- 学部・学年による限定: 卒業を控えた4年生のみを対象としたり、医学部など特定の学部のみで実施されたりするケースも少なくありません。
- 科目による限定: 知識を問う講義科目は対象でも、実験・実習・演習といった、学期を通じた継続的な取り組みが評価される科目は、再試験の対象外となるのが一般的です。
- 単位数上限がある大学: 救済できる単位数に「8単位まで」といった上限を設けている大学もあります。
【確認方法】
まず確認すべきは、あなたのルールブックである「履修要覧(学生便覧)」です。「再試験規程」といった項目を探し、制度の有無と条件を確認しましょう。ポータルサイトに案内が出ている場合もあります。
ルール②:合格しても、成績は「最低評価」になる
再試験はあくまで救済措置です。そのため、たとえ再試験で100点満点を取ったとしても、成績は「可」や「60点」といった、合格ラインぎりぎりの最低評価になるのが一般的です。名古屋大学では「C-」評価となります。
これにより、当然あなたのGPAは大きな影響を受けます。
ルール③:受験料がかかる場合がある
大学によっては、再試験の受験に1科目あたり1,000円〜3,000円程度の費用がかかる場合があります。中には1科目5,000円という大学も存在します。これも、事前に学生便覧や教務課で確認しておくべきポイントです。
「追試験」とは? – やむを得ず休んだ場合の”公式な振替”
一方、追試験は全く意味が異なります。これは、「病気、事故、親族の不幸など、大学が認める『やむを得ない理由』によって、期末試験そのものを受けられなかった学生」を対象とした、公式な振替試験のことです。
こちらは救済措置ではなく、あなたの権利です。しかし、その権利を行使するには、絶対に越えなければならない、非常に厳しい壁があります。
【絶対条件】「公的な証明書(診断書など)」がなければ、門前払い
大学職員として、一番声を大にして言いたいのが、この点です。
「寝坊しました」「勉強不足で…」といった自己都合の理由は、100%認められません。
大学職員として断言しますが、証明書なしで追試験が認められることは絶対にありません。自家用車の渋滞なども認められないことが多いです。「先生に直接お願いすれば、なんとかなるかも…」という淡い期待は、ただちに捨ててください。ルールはルールです。
追試験を申請するには、その理由が「やむを得ない」ものであることを客観的に証明する、公的な書類が”絶対に”必要になります。
- 病気や怪我の場合: 医師が発行した「診断書」(試験日を含む加療期間の明記が求められる)
- 交通機関の遅延: 鉄道会社などが発行する「遅延証明書」
- 親族の不幸(2親等以内が目安): 「会葬礼状」など
「診断書をもらうのにお金がかかるから…」と躊躇する学生がいますが、その数千円をケチったせいで、数万円分の単位を失うことの重大さを理解してください。
【時間との勝負】申請期間は、驚くほど短い
もう一つの重要な注意点が、申請期間です。
多くの大学で、追試験の申請期間は「試験日から3日以内」「1週間以内」など、非常に短く設定されています。
試験を受けられなかった場合は、すぐに大学の履修要覧やポータルサイトで手続きを確認し、教務課の窓口へ直接足を運んでください。「とりあえず、次の授業の時に先生に言えばいいや」と考えていると、手遅れになります。
【要注意】追試験の成績評価と最終ルール
- 成績評価は100点満点ではない場合がある: 追試験は本試験と同じ基準で評価されるのが原則ですが、大学によっては「取得得点の80%」や「満点を90点」とするなど、上限を設けている場合があります。これはGPAに直接影響する重要なルールです。
- 「追試験の追試験」は無い: 指定された追試験日に再度体調不良などで受験できなくても、基本的に「追々試験」は実施されません。追試験が最後のチャンスです。
【比較表】再試験 vs 追試験|あなたはどっち?
ここまで解説した内容を、表にまとめました。自分がどちらに該当するのか、改めて確認してください。
| 比較項目 | 再試験 (Retake Exam) | 追試験 (Make-up Exam) |
|---|---|---|
| 目的 | 不合格者の救済(敗者復活戦) | 欠席者の権利保障(公式な振替) |
| 対象者 | 試験は受けたが、不合格だった学生 | やむを得ない理由で、試験を受けられなかった学生 |
| 必要なもの | 学生証、受験料(大学による) | 公的な証明書(診断書など)、申請書、受験料(大学による) |
| 成績評価 | 合格しても「可」など最低評価が上限 | 原則、本試験と同じ基準。ただし得点に上限を設ける大学あり |
| 実施の有無 | 大学・学部・学年・科目により様々。制度自体がない場合も多い | 大学の規程に基づき、条件を満たせば原則実施される |
それでも単位を落としたら「再履修」– 1年越しの再挑戦
再試験や追試験のチャンスもなく、正式に成績が「不可」となり単位を落としてしまった場合、残された道は「再履修」です。
これは、来年度、もう一度同じ授業をゼロから履修し直すことを意味します。
- 全15回の授業に、もう一度出席する
- すべての課題やレポートを、もう一度提出する
- 期末試験を、もう一度受ける
当然、来年度の時間割は再履修する科目で圧迫されますし、精神的な負担も大きくなります。
そして、最も重要なのがGPAへの影響です。これは大学によって対応が天と地ほど分かれます。
あなたの大学はどちらのタイプか、必ず確認してください。これはあなたの将来に直接関わります。
| GPA処理モデル | 概要 | 学生への影響 |
|---|---|---|
| モデルA:上書き/置換モデル | 不合格(GP=0)となった科目を再履修し合格した場合、当初の不合格評価を累積GPAの計算から除外する。東京大学などがこの形式に近い。 | 初期の失敗が最終的なGPAに与える長期的影響が小さい。最終的な達成度が重視される。 |
| モデルB:永久記録モデル | 不合格(GP=0)となった評価は、再履修・合格後も累積GPAの計算に永久に算入され続ける。宇都宮大学など多くの大学がこの方式。 | 全ての失敗が恒久的に累積GPAを引き下げる。学修過程全体の履歴が重視される。 |
こればかりは一概に言えません。安易に単位を落とすことの代償はあなたが思っている以上に大きいのです。必ず自分の大学の「履修要覧」でGPAの計算方法を確認してください。この違いが、奨学金の申請や大学院進学、就職活動で決定的な差を生む可能性があります。
【大学職員が回答】試験に関する”よくある質問”
Q1. レポートを出し忘れたら、どうなりますか?
A1. 諦めずに、遅れてでも提出すべきです。 提出しなければ評価は確実にゼロ点ですが、遅れて提出すれば減点の上で受理され、部分点がもらえる可能性があります。もちろん、期限を守るのが大前提ですが、「出さない」という選択肢は最悪の結果につながります。まずは謝罪とともに提出しましょう。
Q2. 何も連絡せずに、無断で試験を休んでしまいました…
A2. 問答無用で「不可」です。 追試験の申請資格もありません。これは社会のルールでもあります。必ず事前に連絡を入れるか、事後すぐに手続きを確認する癖をつけましょう。
Q3. 困った時、どう行動すればいいですか?
A3. 行動の順番が重要です。
① まず自分で調べる(履修要覧・ポータルサイトのお知らせを隅々まで読む)
② それでも不明な点があれば「教務課の窓口」へ直接行く
③ 窓口の指示に従う
問い合わせは「最後の手段」です。自分で調べれば1分で分かることを聞きに行くのは、あなたの時間も職員の時間も無駄にしてしまいます。まず公式情報を確認する、という姿勢が何より大切です。
Q4. 教員に連絡するように指示された場合、どう書けばいいですか?
A4. (教務課から、直接教員に連絡して日程調整などを行うよう指示された場合)
以下の例文を参考に、丁寧な言葉遣いを心がけてください。件名と署名で、誰からのメールか一目で分かるようにするのがマナーです。
件名: 【追試験の実施についてのご相談】〇〇学部〇〇学科 学籍番号:〇〇 氏名:〇〇
本文:
〇〇先生いつもお世話になっております。
〇〇学部〇〇学科の山田太郎(学籍番号:1234567)です。先日、教務課にて「〇〇(授業名)」の追試験申請が受理され、試験の実施につきましては、先生に直接ご相談するよう指示をいただきました。
先生には大変ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご都合のよろしい日程など、ご検討いただけますでしょうか。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科
学籍番号:1234567
氏名:山田 太郎
電話番号:090-XXXX-XXXXメール:xxxx@xx.university.ac.jp
Q5. 遠方で窓口に行けません。電話で問い合わせる時の作法は?
A5. やむを得ず電話で連絡する場合は、相手への配慮がより一層重要になります。以下の台本を参考に、要点を簡潔に伝えられるよう準備してから電話しましょう。名乗らない学生が意外と多いですが、絶対にNGです。
電話をかける前の準備
- 履修要覧とポータルサイトの関連情報を全て読んでおく(最重要)
- 学生証
- メモ帳とペン
電話の台本(例)
「お忙しいところ恐れ入ります。私、〇〇大学〇〇学部〇〇学科、学籍番号1234567の山田太郎と申します。期末試験の追試験の件で、手続きについてお伺いしたく、お電話いたしました。ただいま、少々お時間よろしいでしょうか?」(担当者につながったら)
「ポータルサイトの掲示と履修要覧は確認したのですが、〇〇という点について不明なため、ご教示いただけますでしょうか。」
まとめ:最高の大学生活は「知ること」と「行動すること」から始まる
今回は、大学の試験制度、特に「再試験」と「追試験」の違いについて、大学職員の視点から解説しました。
- 再試験は、大学・学部・学年によって制度自体がない、あるいは対象が限定される。もしあっても、成績は最低評価になる救済措置。
- 追試験は、やむを得ず休んだ人向けの公式な振替試験。診断書などの公的証明が必須で、申請期間も短い。成績評価に上限が設けられる場合もある。
- 単位を落とす(不可)と「再履修」となり、GPAへの影響は大学のルール(上書きか、永久記録か)によって天と地ほどの差がある。
- 困ったら、まず「自分で公式情報を調べる」。それでも分からなければ「教務課の窓口」へ。
試験の結果に一喜一憂する前に、まずは自分が今どの状況にいて、どんなルールに基づいて行動すべきかを知ること。そして、正しい手順で行動に移すこと。それが、あなたの大学生活を守る最大の武器になります。
ぜひ、この記事をブックマークして、困った時の「羅針盤」として活用してください。
次のステップへ:関連記事のご案内
- GPAへの影響が気になるあなたへ
- 来年度の履修計画を立て直したいあなたへ
- 大学生活全体の歩き方を知りたいあなたへ
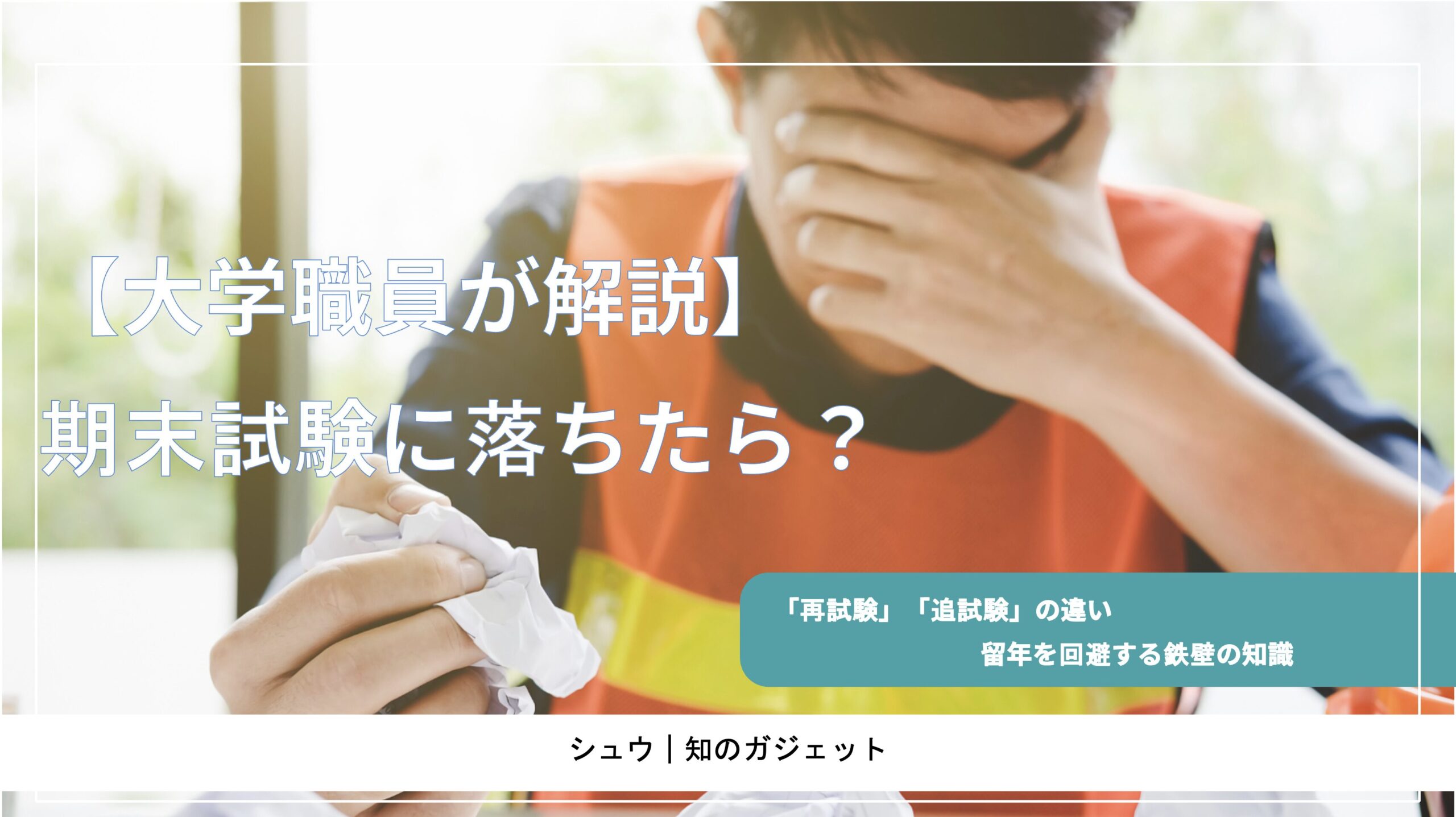




コメント