本ページはプロモーションが含まれています
履修登録の時期、面白そうな授業がたくさんあって『あれもこれも履修したい!』とやる気に満ち溢れていませんか?
あるいは、周りの先輩から『CAP上限ギリギリまで詰め込むのが当たり前』と聞いて、少し焦っていませんか?
その気持ち、よく分かります。しかし、その意欲が、実は留年への第一歩になるかもしれません。
前回の記事【「単位」とは何か?】で学んだ通り、たった2単位の講義には、授業に加えて毎週約4時間もの予習・復習が必要です。その事実を知らずにCAP上限まで履修し、課題地獄に陥り、結果として大量の単位を落としてしまう…。大学職員として、そんな学生を毎年、本当にたくさん見てきました。
この記事では、そんな悲劇を避けるため、大学生活の明暗を分ける重要ルール『CAP制度』について、大学職員である私が徹底解説します。
読み終える頃には、あなたはCAP制度を完全に理解し、自分自身のキャパシティに合った、戦略的で後悔のない時間割を組めるようになっているはずです。
CAP制度とは?大学があなたを守るための「安全装置」です
CAP(キャップ)制度とは、「あなたが1年間(または1学期)に履修登録できる単位数の上限」を定めたルールのことです。
では、なぜ大学はこのような上限を設けているのでしょうか?
それは、前回の記事で解説した「1単位=45時間」の学習時間が根拠になっています。
もし上限がなければ、やる気のある学生ほど多くの授業を詰め込み、結果として一つひとつの学習が疎かになってしまいます。最悪の場合、課題や試験に追われて心身の健康を損なうことにもなりかねません。
CAP制度は、学生がそうした状況に陥るのを防ぎ、質の高い学びを保証するための、いわば大学が用意した「安全装置(セーフティネット)」なのです。
【最重要】まずは、あなたの大学の「CAP上限」を調べよう
この重要なCAP制度ですが、驚くことに、多くの学生が自分の大学の上限単位数を正確に把握していません。
まずは、あなたの大学のルールを確認することから始めましょう。
調べる場所はただ一つ「履修要覧(学生便覧)」
CAPに関するルールは、入学時に配布された「履修要覧」や「学生便覧」といった分厚い冊子に、必ず記載されています。
「履修要覧」が大学4年間のルールブックなら、授業一回ごとのルールブックが「シラバス」です。まだ読んでいない方は、以下の記事も必ずチェックしておきましょう。
多くの場合、「履修について」「履修登録」といった章の中に、「履修登録単位数の上限」や「CAP制度」という項目があるはずです。今すぐ、そのページを開いて、自分の上限単位数にマーカーを引いておきましょう。
大学のWebサイト(学内ポータル)も要チェック
「冊子をなくしてしまった…」という人も安心してください。
ほとんどの大学では、公式Webサイトや学生向けのポータルサイトで、履修要覧のPDFファイルを公開しています。今すぐ検索して、ブックマークしておくことを強くおすすめします。
【体験しよう】あなたの「半期」の履修計画、無理はありませんか?
さて、自分の大学のCAP上限は分かりましたか?
ここからは、その数字を使って、あなたの履修計画が現実に即しているかを、当ブログが開発した「知のガジェット」で体験してみましょう。
ステップ1:年間の上限を「半期」の目安に変換しよう
履修要覧に書かれているCAPは、「年間」の上限(例:48単位)であることが多いです。
しかし、実際の履修登録は「半期」ごとに行いますよね。
ですので、まずはその半分(48単位なら24単位)を、今期の上限の目安と考えましょう。
ステップ2:シミュレーターで「今期の学習時間」を体感しよう
さあ、あなたが「今期、履修しよう」と考えている単位数を、以下のシミュレーターに入力してみてください。
例えば、半期の目安が24単位だとして、少し余裕を持たせて20単位(講義16単位、演習4単位など)を履修するとどうなるでしょうか?
大学・週間&毎日の学習時間シミュレーター
1週間の学習時間(目安)
合計 授業時間
合計 授業外学習(予習・復習など)
平均的な1日の学習時間
授業
0.0時間予習・復習
0.0時間💡 計算のルール
- 半期15週、「1単位=45時間」の国の基準で計算しています。
- 「平日のみ」を選択:全ての学習時間(授業+授業外)を週5日で割ります。
- 「土日も含む」を選択:授業時間は平日(週5日)で割り、予習・復習は土日も使って(週7日)で分散して行う、より現実的なモデルで計算します。
授業種別ごとの時間配分モデル
- 講義:授業1時間に対し、予習・復習が2時間必要です。
- 演習:授業2時間に対し、準備が1時間必要です。
- 実験・実習:授業時間そのものが学修の中心です(3時間)。
結果はどうでしたか?
週に合計〇〇時間、毎日平均〇〇時間の学習が必要だと表示されたはずです。
アルバイトやサークルをしながら、毎週これだけの時間を、あなたは確保できますか?
もう一度、あなたの履修計画が無理のないものか、冷静に見直してみましょう。
「CAP上限まで履修」が危険な、本当の理由
シミュレーターで、CAP上限まで履修した場合の膨大な学習時間を体感していただけたと思います。
それでも「取れるだけ取って、ダメなら落とせばいいや」と考えてしまうのが、新入生が陥りがちな罠です。
その考え方がなぜ危険なのか、あなたの大学生活に直接影響する、3つの決定的な理由があります。
理由①:GPAが下がり、「学内のチャンス」を逃す可能性があるから
GPA(成績の平均値)は、あなたの学業への取り組みを示す、客観的な指標です。
大学によっては、このGPAが学内の様々な場面で活用されることがあります。
例えば、以下のようなケースです。
- 人気のゼミや研究室に所属するための、選考基準の一つになっていること。
- 大学独自の給付型奨学金に応募する際の、学力基準として利用されること。
- 交換留学や海外プログラムへの参加者を選考する際の、判断材料の一つになること。
CAP上限まで履修して各科目の勉強が疎かになり、GPAが下がってしまうと、こうした学内のチャンスを逃してしまう可能性があるのです。
理由②:合計90時間もの「努力」と「時間」が無駄になるから
単位を一つ落とすということは、その科目に費やした全ての時間が「ゼロ」になることを意味します。
前回の記事のルールに則って、2単位の講義科目を一つ落とした場合の損失時間を、正確に計算してみましょう。
- 授業時間: 2時間 × 15回 = 30時間
- 授業外学習(予習・復習): 4時間 × 15回 = 60時間
合計で90時間。これは、丸3日以上に相当する貴重な時間を、完全に無駄にしてしまうということです。
CAP上限まで履修して、もし8単位(4科目)も落としてしまったら、その損失は360時間。考えるだけでも恐ろしいですよね。
理由③:「再履修」という、未来への大きな”負債”を抱えるから
単位を落とすということは、「来年度以降の自分に、その授業を受け直す」という宿題を残すことを意味します。これが「再履修」です。
ここで絶対に勘違いしてはいけないのが、「再履修」の中身です。
- テストだけ受け直せば良い、というものではありません。
- 欠席した授業だけ、出席すれば良いというものでもありません。
「再履修」とは、全15回の授業にゼロから出席し、全ての課題や試験をもう一度受け直すということです。
つまり、来年度のあなたは、
- 来年度の新しい授業
- (落とした単位の)再履修の授業
という、2種類の授業を同時にこなさなければなりません。
これは、あなたの時間割を圧迫し、来年度の学習計画に大きな負担をかける、未来の自分への「負債」そのものなのです。
万が一、履修計画に失敗してしまい『このままでは単位を落としそうだ』と感じた時のために、多くの大学には『履修取り消し』という最終手段が用意されています。これは、指定された期間内であれば、ペナルティなしで履修をキャンセルできる制度です。これも重要なルールなので、履修要覧で確認しておきましょう
【大学職員が推奨】1年生の履修登録、最適な単位数は?
では、具体的にどれくらいの単位数を履修するのが良いのでしょうか。
私がお勧めするのは「CAP上限マイナス4~8単位」を、最初の目安とすることです。
その理由は、以下の3つです。
- 大学生活に慣れるための時間を確保するため
- サークルやアルバイトなど、課外活動に打ち込む余裕を作るため
- 万が一単位を落とした際の「再履修枠」という最強の保険を確保するため
では、具体的にどのような授業を、どの順番で履修していけば良いのでしょうか。 その「道しるべ」となるのが、大学が示している「履修モデル」や「カリキュラムツリー」です。
近日中に公開予定の『【大学の羅針盤】「履修モデル」と「カリキュラムツリー」の賢い使い方』で、4年間の学習計画を立てるための具体的な方法を解説しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。
まとめ
今回は、大学の履修登録における重要ルール「CAP制度」について解説しました。
- CAP制度は、学生の学びの質を守るための履修上限ルールである。
- 自分の大学のCAP上限は「履修要覧」で必ず確認すること。
- シミュレーターで、CAP上限まで履修した場合のリアルな学習時間を体感しよう。
- CAP上限ギリギリの履修は「再履修の余裕」がなくなり非常に危険。
- 1年生は「CAP上限マイナス4~8単位」を目安に、余裕を持った時間割を組むのが賢い戦略。
ぜひ、この記事とシミュレーターを活用して、あなたの4年間を豊かにする、後悔のない履修計画を立ててください。
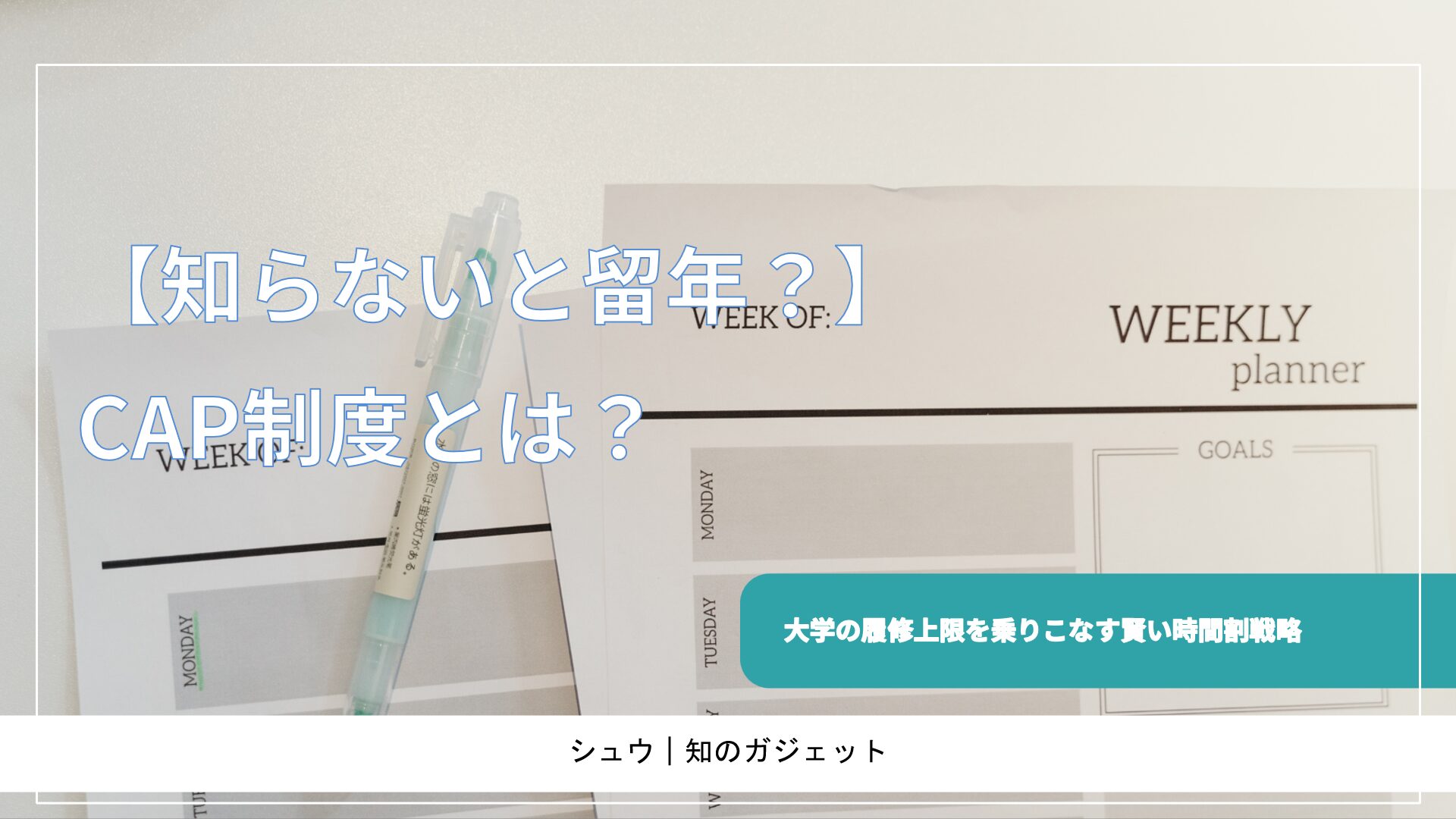



コメント