「子供の将来のためにも、大学には行かせてあげたい」
多くのお父さん、お母さんが、そう願っていると思います。
でも、テレビやネットで「教育費は1人1000万円以上」なんて話を聞くと、 「我が家の家計で、本当にそんな大金を準備できるのだろうか…」 と、漠然とした不安を感じてしまいますよね。
この記事では、そんなお父さん、お母さんのために、 10年以上にわたって大学職員として多くの学生と保証人を見てきた私が、 大学進学にかかる「リアルな費用」と、「いつから、どのように」準備を始めれば良いのかを、分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたの不安は、 具体的な「目標」と「計画」に変わっているはずです。
衝撃!大学4年間でかかる費用は、最低でも約250万円から
まず、知っておくべき「リアルな数字」からお話しします。
ひとくちに大学の費用と言っても、国公立か私立か、文系か理系かで、金額は大きく変わってきます。
国立大学の場合:約243万円
最も費用を抑えられる国立大学でも、入学金と4年間の授業料を合わせると、合計で約243万円が必要です。
これが一つの大きな目標金額になりますね。
私立大学の場合:約400万円~550万円
私立大学の場合は、さらに大きな金額が必要になります。
文系学部であれば約408万円、実験や設備費がかかる理系学部では約551万円が、4年間の学費の平均的な目安です。
見落としがちな「プラスα」の費用
さらに、忘れてはいけないのが、大学に合格する前にかかる「受験費用」です。
受験料だけでなく、遠方の大学を受ける場合は交通費や宿泊費もかかり、平均して30万円ほど準備しておく必要があります。
また、教育プランによっては、これ以上の費用がかかるケースも考えておきましょう。
- 6年制の学部:医学部・歯学部・薬学部・獣医学部などは、修業年限が6年間。学費も単純に1.5倍以上になります。
- 大学院への進学:もし、お子さんが研究の道に進みたいと願った場合、修士課程(2年)、博士課程(3年)と、さらに5年間の学費が必要になる可能性も。
- 留年・休学:万が一の留年や休学でも、追加で在学費用がかかることも忘れてはいけません。
結論:大学費用の準備は「早ければ早いほど良い」3つの理由
先ほど紹介した数百万円という金額を見て、「そんな大金、今から準備できるわけがない…」と、圧倒されてしまったかもしれません。
でも、大丈夫です。なぜなら、あなたには「時間」という最強の味方がいるからです。
理由①:時間を味方につけて、お金に働いてもらえるから
例えば、月々3万円を貯金する場合を考えてみましょう。
10年間続ければ、3万円 × 12ヶ月 × 10年 = 360万円になります。
これを、NISAなどの「積立投資」で、もし年利5%で運用できれば、同じ積立額でも、10年後には約465万円に増える計算です。(※これはあくまでシミュレーションです)
早く始めれば始めるほど、この「時間がお金を生む力」を最大限に活用できるのです。
ちなみに、我が家では現在、毎月10万円を積立NISAでこつこつ運用しています。(この具体的な話は、また別の記事で詳しく…!)
理由②:毎月の家計への負担を、軽くできるから
もし、大学入学直前の3年間で360万円を貯めようとすると、毎月10万円も貯金しなければならず、家計は火の車です。
実は私も、一人目の子供が早くに生まれたこともあり、当時は全く貯金ができていませんでした。
だからこそ、早くからコツコツ準備することで、未来の家計と、なにより心の余裕が生まれることの重要性を、実感しているんです。
理由③:子供の「やりたい!」という夢を、お金で諦めさせずに済むから
これが、一番大切な理由かもしれません。
いざ、あなたのお子さんが「〇〇大学の理系学部で、最先端の研究がしたい!」と目を輝かせた時。
「ごめん、うちには私立の理系に行かせるお金はないんだ…」
なんて、言いたくないですよね。
早くから準備をしておくことは、子供の可能性という、未来への最高の投資なのです。
どうやって準備する?3つの基本的な方法
では、具体的にどのような方法で準備していけば良いのでしょうか。
代表的な3つの方法をご紹介します。
それぞれの方法にメリット・デメリットがありますが、詳しい比較はまた別の記事でお話ししますね。
今回は、まず「こんな方法があるんだな」と知っていただくのが目的です。
方法①:学資保険
昔からある、最も代表的な方法が「学資保険」です。
毎月決まった保険料を支払うことで、子供が18歳になるなどのタイミングで、満期金としてまとまったお金が受け取れます。
貯蓄と同時に、親に万が一のことがあった場合の保障も兼ね備えているのが特徴です。
方法②:つみたてNISAを活用する
最近、利用者が急増しているのが、NISA制度を活用した「積立投資」です。
学資保険よりも大きなリターンが期待できる可能性がある一方で、元本割れのリスクもゼロではありません。
ちなみに、我が家もこの「積立投資」をメインで実践しています。
もし、読者の方の中にも、すでにNISAを始めている方がいらっしゃれば、その一部を教育資金と考えるのも良い方法です。
方法③:銀行預金
最もシンプルで、安全なのが「銀行預金」です。
毎月、決まった額を、子供名義の口座などに貯めていきます。
元本割れのリスクは絶対にありませんが、現在の低金利では、お金がほとんど増えないというデメリットがあります。
まとめ:大切なのは、今日から「第一歩」を踏み出すこと
今回は、子供の大学費用という、少し気の重くなるテーマについて、リアルな数字と具体的な準備方法を見てきました。
数百万円という金額に、改めて驚かれたかもしれません。
しかし、最も大切なのは、今日、この瞬間から「我が家の場合はどうだろう?」と考え、行動を始めることです。
まずは、あなたの家庭の目標額を決め、月々いくらなら準備できそうか、シミュレーションしてみる。
その小さな第一歩が、数年後、あなたのお子さんの夢を支える、大きな力になります。
この記事が、そのきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。
▼お金の次に考えるべき、大学生活の全て▼
この記事では、大学生活の「費用」という、土台となる部分を解説しました。
大切なお金と時間を最大限に活かすために、履修登録やPC選びといった、大学生活のあらゆる側面について解説した『大学生活の教科書』も、ぜひお子さんと一緒にご覧ください。
4年間を後悔しないための、大学職員からの全ての知恵が詰まっています。
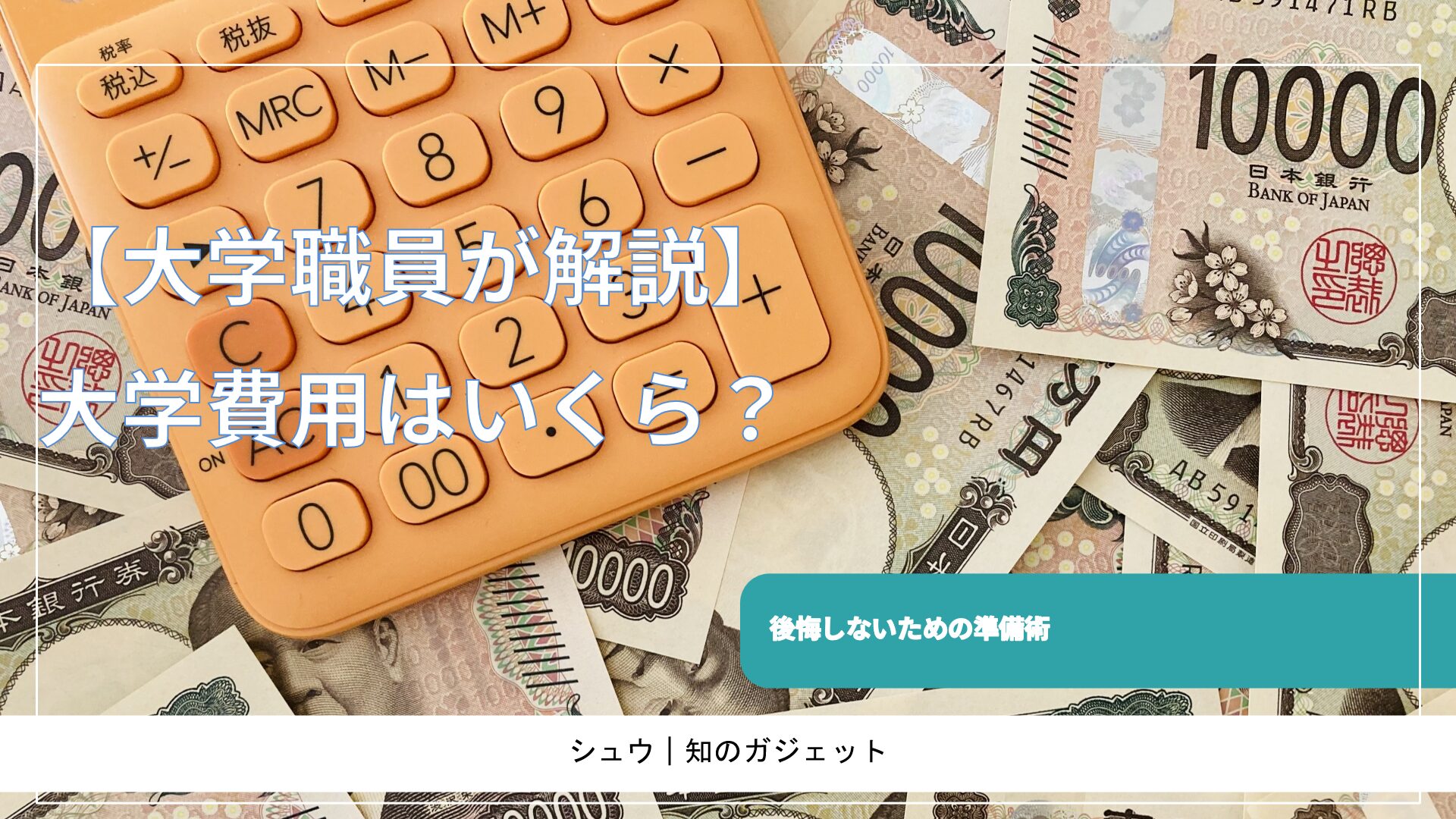


コメント