本ページはプロモーションが含まれています
「大学に入学したものの、『単位』『フル単』『落単』…よく分からない言葉ばかりで、少し不安になっていませんか?」
「高校までとは全く違う、大学の授業の仕組みや成績の決まり方に、戸惑いを感じていませんか?」
その気持ち、とてもよく分かります。大学職員として毎年多くの新入生を迎えていますが、ほとんどの学生があなたと同じように、大学独自のルールに戸惑うところからスタートします。
実は、多くの新入生がこの『単位』というルールの本質を知らないまま大学生活をスタートさせ、1年生の終わり頃に「こんなはずじゃなかった…」と後悔するケースは少なくありません。大学職員として、そんな学生を何人も見てきました。この『単位』というルールの本質を知っているかどうかで、あなたの4年間は天国にも地獄にもなるのです。
でも、もう大丈夫です。
この記事では、大学職員である私が、全ての土台となる『単位』の仕組みについて、最新の情報を交えながら、どこよりも詳しく、そして分かりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたは単位のプロになり、自信を持って大学生活の第一歩を踏み出せるようになっているはずです。
結論:「単位」とは、学修の「量」を測る全国共通の物差しです
早速、結論からお伝えします。
大学における「単位」とは、あなたが特定の学問分野を、どれくらいの時間をかけて学んだかという「学修の量」を、客観的な数値で示したものです。
これは、戦後の大学制度改革でアメリカの単位制度(クレジットシステム)を導入したことに由来し、今では日本全国どの大学でも通用する共通の指標です。卒業や資格取得の条件となる、極めて重要なものだと考えてください。
まず、高校までの「授業に真面目に出席していれば、なんとかなる」という考え方は、一度リセットしてください。
大学は、単に授業を受ける場所ではありません。教員から与えられたテーマについて、自分で調べ、考え、学ぶという「主体的な学習」に対して、その成果を「単位」という形で認定する場所なのです。この「主体的な学び」こそが、近年の大学教育で最も重視されているポイントです。
法律で決まっている「1単位=45時間」という絶対ルール
「学修の量を示すのが単位だということは分かったけど、じゃあ具体的にどれくらい勉強すればいいの?」
そう思いますよね。
実は、この学修時間は、国が定める「大学設置基準」という省令(法律に準ずるルール)で、明確に決められています。大学職員として、まずあなたに知っておいてほしい、最も重要なルールです。
(大学設置基準 第二十一条 2項)
[cite_start](…略)一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、(…後略) [cite: 5]
難しく書いてありますが、ポイントは一つだけです。
1単位を修得するためには、合計45時間の学修が必要である
これが、日本の全ての大学に共通する、絶対的な大原則なのです。
「90分授業=2時間」のカラクリ
「45時間も勉強が必要なの?」と驚く前に、大学特有の時間の考え方を知っておきましょう。
多くの大学では、授業時間を「時限(じげん)」や「コマ」という単位で管理しています。そして、大学のルール上、1時限あたりを約50分として計算していることがほとんどです。
皆さんが受けている「90分授業」は、この「時限」を2つ分まとめたもの。厳密には「授業45分+休憩時間5~10分+授業45分」といった構成になっており、大学の単位計算上は「2時間(2時限)分の授業」として扱われます。これが、新入生が抱きがちな「90分なのに2時間扱い?」という疑問の答えです。
【最重要】「1単位=45時間」の本当の内訳とは?
ここからが本題です。
「1単位=45時間」の学修が必要で、その時間には授業に出席している時間だけでなく、予習や復習といった「授業外での学修」も含まれています。
そして、授業の種類によって、この「授業時間」と「授業外学修」の比率の考え方が異なります。かつては大学設置基準で授業形態ごとに時間の目安が定められていましたが、2022年(令和4年)の基準改正により、その規定は撤廃されました。
この改正は、オンライン授業の普及など、多様な授業形態に柔軟に対応するためのものです。しかし、「1単位=45時間の学修」という大原則は変わっていません。むしろ、各大学や教員が、シラバスを通じて学生に学修時間の内訳をより明確に説明する責任が重くなったと言えます。
以下に、現在でも多くの大学で採用されている、標準的な3つのモデルを紹介します。
パターン①:講義(座学で知識をインプットする授業)
1単位の内訳(標準モデル): 授業時間15時間 + 授業外学修30時間 = 合計45時間
「講義」は、教員の話を聞いて知識をインプットすることが中心の、いわゆる一般的な「授業」です。この形式では、予習・復習といった「授業外学修」に、授業の倍の時間をかけることが標準的なモデルとされています。
これを、一般的な「90分(2時間)×15回」の講義に当てはめてみましょう。なぜこの授業が「2単位」になるのか、その計算式は以下の通りです。
- 授業時間: 2時間 × 15回 = 30時間
- 授業外学修: 30時間(授業時間) × 2(倍) = 60時間
- 合計学修時間: 30時間 + 60時間 = 90時間
この「90時間」という合計学修時間が、「2単位」分(45時間/単位×2)の学修量にぴったり相当します。これが、多くの講義科目が「2単位」で設定されている理由です。
パターン②:演習(ディスカッションや発表など、実践的な授業)
1単位の内訳(標準モデル): 授業時間30時間 + 授業外学修15時間 = 合計45時間
「演習(ゼミ)」は、学生が主体となってディスカッションや発表、グループワークを行う、より実践的な授業です。授業時間そのものがアウトプットの場となるため、授業時間の比率が高く設定されています。準備のための授業外学修は、授業時間の半分が目安です。
パターン③:実験・実習・実技(実際に手を動かす授業)
1単位の内訳(標準モデル): 授業時間30~45時間 + 授業外学修15~0時間 = 合計45時間
資格取得に関わる実習や、理系の実験、体育などの実技は、授業時間そのものが学びの主体と見なされることが多いです。そのため、授業外学修の比率は講義に比べて低く設定される傾向にあります。
| 授業形態 | 1単位あたりの 標準的な授業時間 |
1単位あたりの 標準的な授業外学修 |
合計学修時間 | 主な内容 |
|---|---|---|---|---|
| 講義 (Lecture) | 15時間 | 30時間 (授業の倍) | 45時間 | 知識のインプット、理論の学習。予習・復習が不可欠。 |
| 演習 (Seminar) | 30時間 | 15時間 (授業の半分) | 45時間 | 発表、討論、グループワーク。授業内での主体的な活動が中心。 |
| 実験・実習・実技 (Lab/Practical) | 30~45時間 | 15~0時間 | 45時間 | 実際に手を動かす作業。授業時間そのものが学びの主体。 |
注: これらの時間は、多くの大学で採用されている標準的な考え方を示すものです。2022年の大学設置基準改正により、大学はより柔軟に授業を設計できるようになりました。あなたの授業の正確な内訳は、必ずシラバスで確認してください。
シラバスは、あなたと大学との「契約書」である
「じゃあ、私が受けている授業はどのパターンなの?」
「どれくらい予習・復習すればいいの?」
そう思ったら、すぐにシラバスを確認してください。
▼あわせて読みたい
「そもそも、シラバスのどこをどう読めばいいか分からない…」という方は、まずはこちらの記事で『大学職員が教えるシラバス読解術』をマスターすることをおすすめします。
法的なルールが柔軟になった今、シラバスは単なる授業計画書ではありません。その授業で単位を修得するために「何を」「どれくらい」「どのように」学修する必要があるかを示した、あなたと大学・教員との間の「学修に関する契約書」とも言える、極めて重要な文書です。
シラバスには、以下の情報が必ず記載されています。
- 授業形態: その授業が「講義」「演習」「実習」のどれにあたるか。
- 到達目標: この授業を終えたときに、あなたが何ができるようになっているべきか。
- 成績評価の方法・基準: 試験、レポート、発表など、何がどれくらいの割合で評価されるか。
- 授業計画と授業外学修の指示: 各回の授業内容と、それに必要な予習・復習の具体的な指示。
成績評価は、このシラバスに書かれた「到達目標」を達成できたかどうかで決まります。つまり、シラバスを熟読し、そこに書かれた学修を実践することが、単位修得への最も確実な道筋なのです。
大学の勉強は「授業の外」が本番である
ここまで読んでくださったあなたは、もうお分かりですね。
大学の勉強において、特に「講義」科目では、授業に出席している時間の2倍もの時間が「授業の外」で必要になる、ということです。
これは、国が大学教育に「受動的な知識の暗記」から「生涯学び続ける、主体的に考える力の育成」へと、質的な転換を求めているからです。大学の先生は、あなたが毎週、予習・復習をやってきている前提で授業を進めます。
90分の授業は、あくまでヒントを得る場所、思考のきっかけを得る場所に過ぎません。本当の学びは、図書館や自宅で、一人静かに教科書や資料と向き合う、「自学自習」の時間にあるのです。
高校までの「受け身」の勉強スタイルから、大学での「主体的」な学びのスタイルへ。
ぜひ、この「単位」の本当の意味を理解して、意識を切り替えてみてください。
まとめ
今回は、大学生活の全ての土台となる「単位」について、その本質を解説しました。
- 単位は、あなたの「学修の量」を示す全国共通の指標である。
- 国が定める大学設置基準により「1単位=45時間」の学修が必要とされている。
- 45時間には、予習・復習などの「授業外学修」も含まれている。
- 授業形態(講義・演習・実習)によって、授業時間と授業外学修の標準的な比率が異なる。
- シラバスは、その内訳を示す「契約書」。必ず熟読すること。
- 大学での学びは「授業の外」にある自学自習が本番になる。
まずは、自分が履修している科目のシラバスを開いて、「単位数」と「授業形態」、そして「授業外学修の指示」を改めて確認してみましょう。きっと、今日の話を聞いた後では、シラバスが全く違って見えてくるはずです。
ちなみに、シラバスの具体的な読み解き方や、後悔しない授業選びのコツについては、以下の記事で徹底的に解説しています。ぜひ、あわせてお読みください。
そして、単位の本当の意味が分かったあなたに、次にお伝えしたいのが、大学生活の明暗を分けるもう一つの重要ルール『CAP制度(履修登録単位数の上限)』です。
1年間にどれだけ多くの単位を履修できるかを制限する、このルールの本質を知らずして、後悔のない時間割を作ることはできません。
近日中に公開予定の『【知らないと留年?】CAP制度とは?後悔しないための時間割の作り方』で、最高のスタートを切るための戦略を解説しますので、ぜひ楽しみにお待ちください。
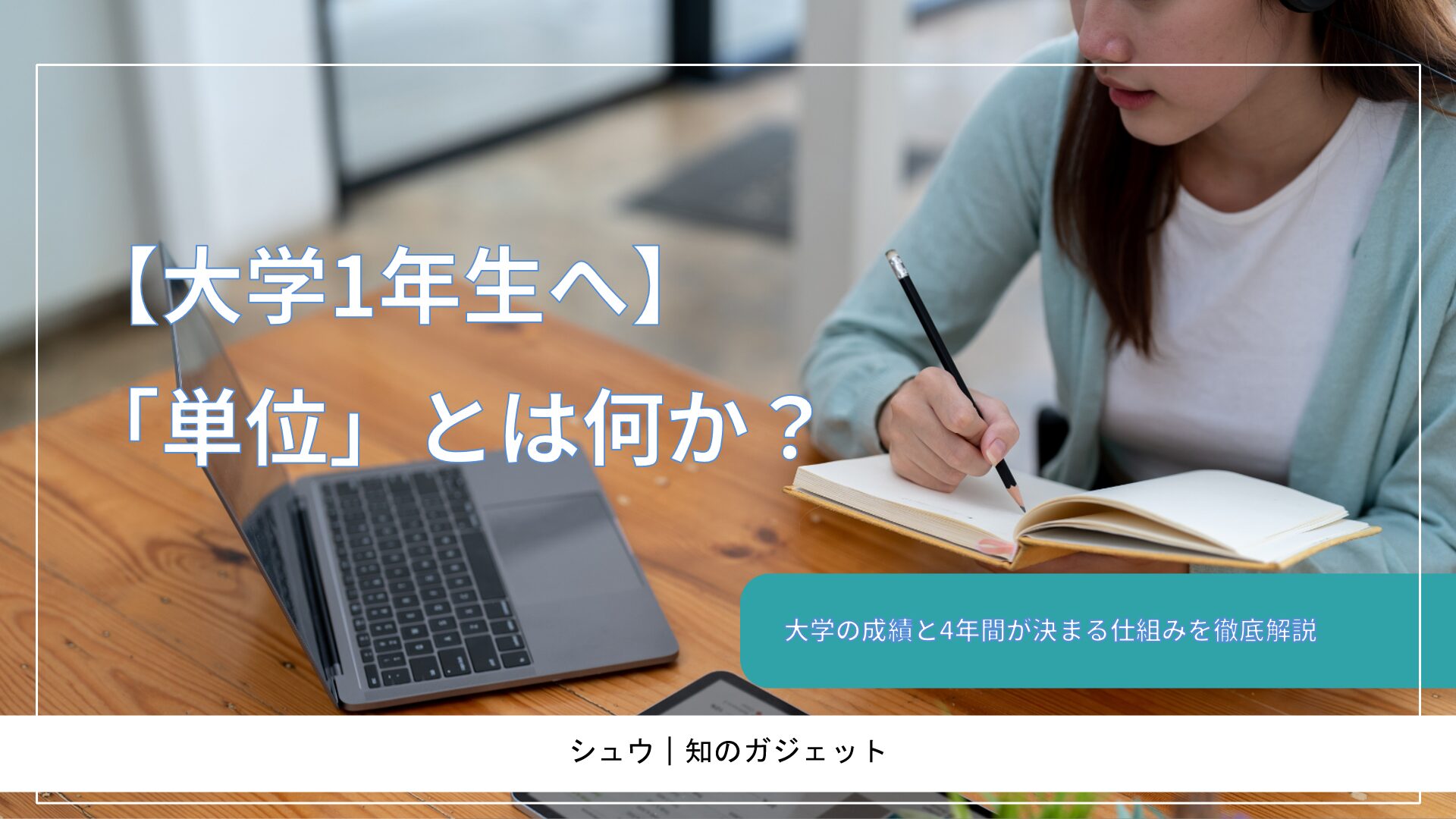



コメント