こんにちは、「大学職員パパ」のシュウです。
これまでの記事で、「シラバスの正しい読み方」 や、「卒業要件の確認方法」 といった、大学生活の土台となるルールについて解説してきました。
今回は、その総仕上げ。多くの学生が気にしてやまない、『GPA(Grade Point Average)』との正しい向き合い方について、お話しします。
「GPAが高い方が有利」という、危険な思い込み
「GPAは、高ければ高いほど良い」 「GPAが低いと、就活で不利になる…」
あなたも、そう思っていませんか?GPAの数字に一喜一憂し、少しでも評価を上げようと、SNSで「楽単(楽に単位が取れる授業)」の情報を必死で探したり…。
その気持ち、痛いほど分かります。
しかし、僕は大学職員として、10年以上、何千人という学生の成績と、その後の進路を見てきました。 だからこそ、あなたに警告しなければなりません。
ただ数字だけが高いGPAには、何の意味もありません。
その考え方のままでは、いざ就職活動の面接で「あなたの強みは何ですか?」「大学で何を学びましたか?」と問われた時に、何も語ることができない、空っぽの学生になってしまいます。
この記事を読めば、あなたがGPAという呪縛から解放され、自信を持って自分の学びを語れるようになることを、お約束します。
そもそもGPAとは何か?大学が導入した本当の理由
多くの学生が、GPAを単なる「成績の平均点」だと思っていますが、その本質は少し違います。
GPAとは、一つひとつの科目の成績を、国際的に通用する客観的な数値(GP)に置き換え、その平均を算出したものです。
これは、「一夜漬けの試験対策」だけでなく、「学期を通した継続的な努力」を評価するために導入された仕組みなのです。
大学があなたに求めているのは、目先のテストの点数ではありません。 授業に真摯に取り組み、課題と向き合い、知的好奇心を持って学びを深めていく、その「学問への姿勢」そのものなのです。
GPA至上主義が、あなたを不幸にする「3つの罠」
「とにかくGPAさえ高ければいい」という考え方は、あなたの可能性を狭める、非常に危険な「罠」です。
罠1:「楽単」ばかり履修し、学びの機会を失う
これが、最も多くの学生が陥る罠です。 GPAを上げるためだけに、興味のない「楽単」ばかりを履修する。
思い出してください。あなたが大学の一つの授業に支払っている本当の値段を。 その貴重な「時間」と「お金」を、ただ座っているだけの退屈な授業に投資して、本当に良いのでしょうか?
それでは、お金を払って、学びの機会をドブに捨てているのと同じです。
罠2:挑戦を恐れ、成長が止まる
「この授業は面白そうだけど、評価が厳しいらしいからやめておこう…」 「A(優)が取れないかもしれないから、別の簡単な授業にしよう」
このように、GPAが下がることを恐れて、知的な挑戦から逃げていませんか?
本当の成長は、少し背伸びをした、困難な課題に挑戦する中でしか得られません。失敗を恐れて安全な道ばかりを選んでいては、あなたは4年間、まったく成長できないでしょう。
罠3:就活で「なぜ?」に答えられなくなる
これが、GPA至上主義の、最終的な末路です。 企業の採用担当者は、あなたのGPAの「数字」だけを見ているわけではありません。彼らが見たいのは、その「数字の裏にある物語」です。
「あなたのGPAは3.8と非常に優秀ですが、特に力を入れた科目は何ですか?」 「その学びを通じて、あなたは何を得ましたか?」
この問いに、あなたはどう答えますか? 「楽な授業を選んで、良い成績を取りました」なんて、口が裂けても言えませんよね。中身の伴わない高いGPAは、かえってあなたを追い詰めることになるのです。
就活で本当に評価される、価値ある成績証明書の作り方【GPA戦略】
では、私たちはGPAとどう向き合えばいいのでしょうか。 それは、「GPAを、あなたの学びの物語を証明するための、ポートフォリオとして戦略的に構築する」という視点を持つことです。
戦略1:土台となる「必修科目」で、SかA(秀か優)を狙う
まずは、以前の記事でも強調した「必修科目」。
これは、あなたの専門分野の根幹をなす、最も重要な科目です。
ここできっちりと最高評価(SやA)を取ることで、「私は、自分の専門分野の基礎を、完全に理解しています」という、何より雄弁な証明になります。ここは絶対に、手を抜いてはいけません。
▼必修科目については次の記事を参照
戦略2:自分の「好き」を貫く、「挑戦科目」を持つ
次に、たとえ最高の評価が取れないかもしれなくても、「心から面白いと思える、挑戦的な科目」を、いくつか履修しましょう。
それが、あなたの知的好奇心や、主体的に学ぶ姿勢を証明する「武器」になります。
面接で、「この科目はB評価ですが、なぜ履修したのですか?」と聞かれた時こそ、チャンスです。 「評価のことは気にせず、どうしてもこの分野を深く学びたいという思いから挑戦しました。結果としてB評価でしたが、〇〇というスキルや、△△という視点を得ることができ、私にとって最も価値のある授業の一つでした」 と語れば、採用担当者は、あなたのGPAの数字以上に、その挑戦する姿勢を高く評価するはずです。
戦略3:GPAを「平均点」ではなく「分布」で見る
自分の成績を、ただ一つのGPAの数字で見るのはやめましょう。
- 専門の必修科目は、ほとんどS(秀)
- 興味のある選択科目は、A(優)が多い
- 少し苦手だが挑戦した科目は、B(良)がいくつかある
このように、自分の成績に「メリハリ」がある状態が、最も理想的です。 それは、あなたが何も考えずに授業を選んだのではなく、「自分の軸を持ち、戦略的に履修を組み立てた」ことの、何よりの証拠となるからです。
まとめ:GPAは、あなたの「学びの物語」そのものである
今回は、多くの大学生を惑わす「GPA」との正しい向き合い方について解説しました。
- GPAは目的ではなく、あなたの学びを可視化する「ツール」である。
- GPAの数字だけを追い求めると、学びと成長の機会を失う。
- 重要なのは、GPAの「数字」ではなく、その裏にある「物語」を語れること。
- 「必修」で土台を固め、「挑戦科目」で個性を出す、戦略的な履修を心がける。
GPAは、あなたを縛るためのものではありません。 あなたが4年間で、何を考え、何に挑戦し、何を学んできたのか。その「知的な冒険の記録」そのものです。
ぜひ、この記事と、これまでのシリーズ記事を参考に、あなただけの、価値ある物語を紡いでいってください。
▼大学生活の「契約書」を読み解く▼
▼4年間の「設計図」を描く▼
さて、これにて「シラバス」「卒業要件」「GPA」という、大学生活の根幹をなす3つのテーマについての解説が終わりました。
▼お待たせしました!「大学生活の教科書」が完成しました▼
この記事で解説した「GPA戦略」を含め、シラバスの読み方から、PC選び、費用面まで、大学生活の全ての悩みをこの記事一本で解決する『大学生活の教科書』がついに完成しました。
最高の4年間を送るための完全なロードマップです。ぜひ、あなたの大学生活の羅針盤としてご活用ください。
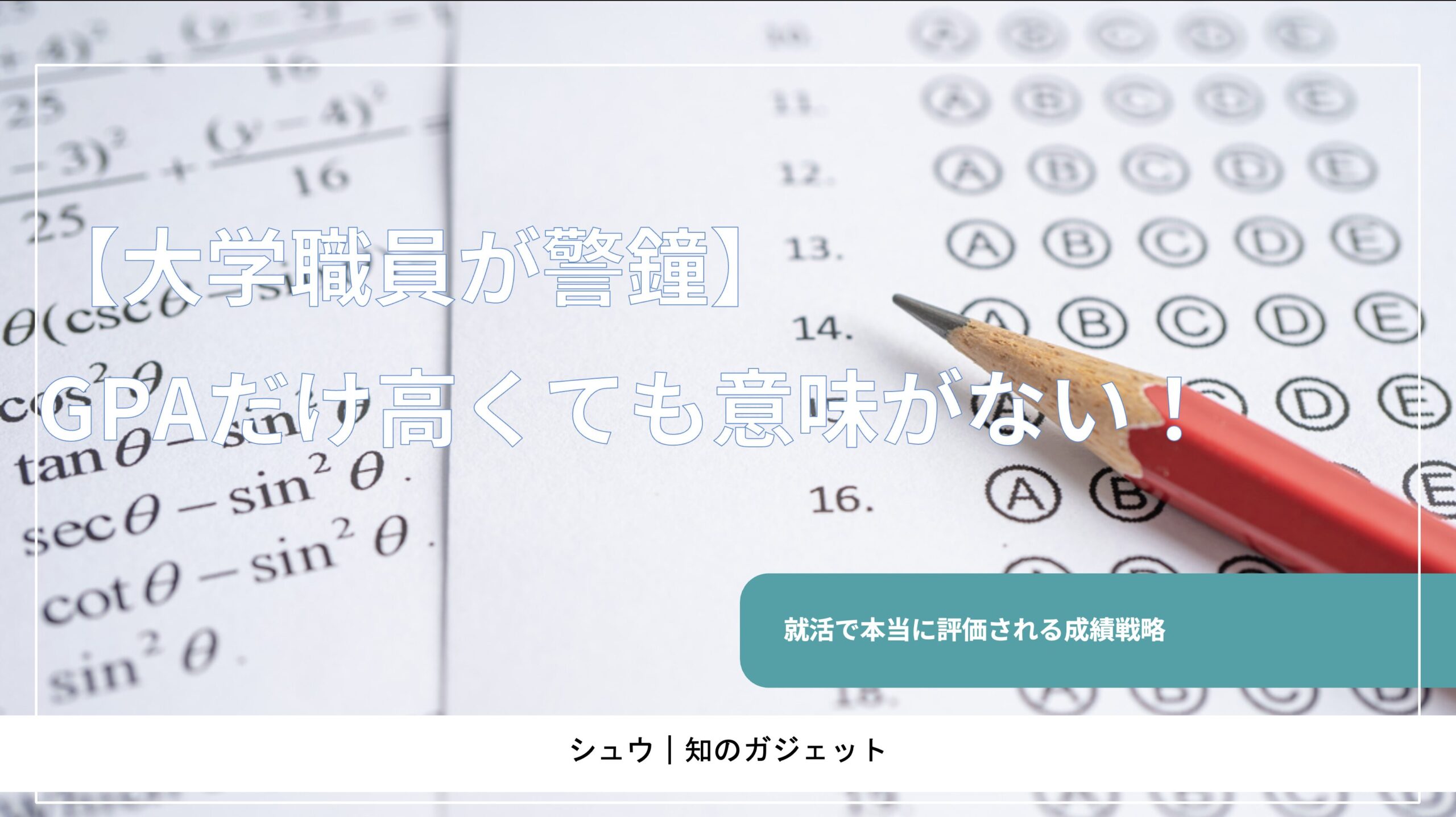





コメント